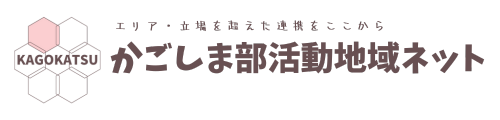始めの一歩をお手伝い
いよいよ令和8年度から6年間、部活動の地域展開は「改革実行期間」となり、どの地方公共団体も確実に休日の地域展開等に着手とされています。(「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」最終とりまとめより)
国の指針において現在(令和7年度9月時点)は、それぞれの地域に合った形での運営を検討してください、とのことで各地域でモデル事業等の取り組みが行われています。
何が正解か、やってみないとわからない、というのが正直なところでしょうか。さて、直面した学校や部活動は具体的には何をどうしたらいいのでしょうか。
地域展開という事なので、まずは、地域に目を向けてみる必要がありそうです。校区内、または近隣に既に地域クラブがある場合、何の競技があり、どのような条件で利用ができるのか等調査し、地域クラブと協議する場を設けるのもいいと思います。
地域クラブとクラブチームの違いについては、これから国がガイドラインを整備し、認定制度が整っていくようです。
競技によっては、地域クラブが無いものもあると思います。受け皿が見つからない場合、新しく地域クラブを立ち上げるという方法も考えられます。校区の地域コミュニティ協議会等と連携して共同で運営を行ったり、または、部活動単位でそのまま地域クラブになることも可能だと思います。
これはスポーツ少年団の活動をイメージしてみると分かりやすいので例にすると、スポーツ少年団は全国で展開されている青少年のスポーツ団体で、その理念の下に各単位スポーツ少年団が活動しています。
その多くは学校施設を活用し(抽選等申込し)、各少年団ごとに運営を行っています。代表は指導者(監督)や保護者会長が担い、部費の集金、保険の契約、大会の参加申込、協会への選手登録、指導者へのお礼、消耗品の購入等を独自に行っているところがほとんどではないでしょうか。この仕組みを中学校の部活動地域展開に応用することができれば、世代が変わっても引継ぎながら継続して活動を行う事が可能になるのではないかという考え方です。
とはいえ、運営を始めるには、多くのことを検討し、決めていかなくてはなりません。いつから、どこで、誰が、何を、どのように。この細かい決め事をする間も、子ども達の時間は動き続けます。
私たちは、部活動の改革期における団体運営のサポート事業を行い、途切れることなく子ども達の活動が行えるようお手伝いしていきたいと思っています。地域クラブにおいての、主に事務的な作業を整理し、いずれは地域クラブ独自での運営が行えることを目指しサポートします。
【制度に合わせて事務的作業を整備できるよう準備中です】